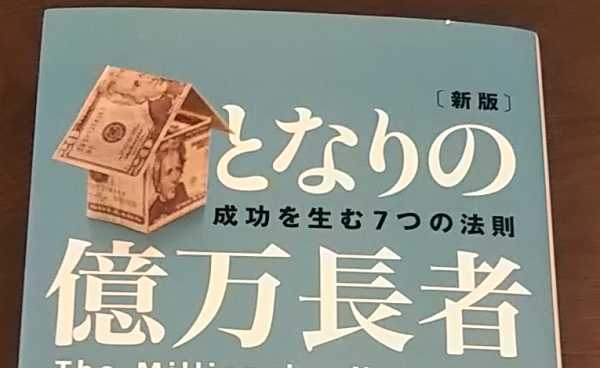
「となりの億万長者~成功を生む7つの法則~」を読みましたのでご紹介します。
管理人は、普段は図書館で本を借りていますが、この本からはあまりにも感銘を受けることが多いので、図書館で2回借りた後ついに買いました。
アメリカの億万長者について書かれていますが、日本でも十分通用する内容ではないでしょうか。
そして本書は、資産を築くための一助になりますので、ご一読をお勧めします。
感想を書いていたら纏まりが無くなってきたので、気に入った文章だけ書き抜いて紹介しています。
目次
期待資産額
本書では、1代でも資産が築けるレベルとして、100万ドル〜1,000万ドルの資産を持つ人をターゲットとしている。
その他、金持ちかどうかを計るもう一つの味方として、「期待資産額」を基にしている。
資産の額は、その人の年齢と収入に大きく影響され、収入が多ければ資産も多いはずだし、働いた年月が長ければそれだけ蓄財も出来ているはず。
期待資産額=年齢×年間家計所得(税引前)÷10
(例:50歳×年収800万円÷10とすると、期待資産額は4,000万円)
※自分の資産を計算するときは、遺産相続がある場合はその分を引いて計算します。
蓄財優等生:期待資産額の2倍以上の資産を保有
蓄財劣等生:期待資産額の半分以下しか資産を保有していない。
蓄財優等生は、同じ所得層、年齢層の中で、資産形成の上手な人々。
 おとうふ
おとうふ
蓄財に目覚めるのが遅かったので、巻き返し中です。。。
イントロダクション
本書では、アメリカ富裕層研究の第一人者である著者が、1万人以上の億万長者にインタビューを行い、資産・年収・職業・消費行動等を調査した結果が紹介されている。
調査結果は、億万長者の多くが、ありふれた職業や家庭を持つ「普通の人々」だった。
本書では、調査結果を基に億万長者の日常の暮らしぶりから学ぶべき「7つの法則」を導き出している。
我々も、億万長者の生活を真似ることにより、資産を築く一助になる。
アメリカ人の大半はお金持ちの家庭の行動を全く知らない。
広告業界や映画業界は、お金持ちになればお金を湯水のごとく使うものだと見事に我々の頭に刷り込んでしまった。
だが、お金持ちの多くは、資産額に比べてはるかにつつましい生活をしている。
資産とは貯めるものであって、使うものでは無い。
どうしたら金持ちになれるか?
金持ちになるには、幸運、遺産、高学歴、頭の良さが条件ではない。
勤勉、我慢、計画性などのライフスタイルから資産は形作られていく。
そして自分を律する強い精神力を持つことが何よりも重要だ。
今回の調査で、次の7つのポイントが資産を築く成功の秘訣だということが分かった。
- 収入よりはるかに低い支出で生活する
- 資産形成のために、時間を使う
- 世間体を気にしない
- 社会人となった後、親からの経済的な援助を受けていない
- 経済的に自立するよう、子供たちを育てる
- 上手にビジネスチャンスを掴む
- 時代にマッチした職業に就く
資産家の研究で分かったことは、資産を築くには自分をコントロールする精神力、犠牲をいとわぬ態度、そして勤勉さが必要であること。
1.収入よりはるかに低い支出で生活する
時間と金をかけて趣味の良いものを身につければ、その分お金が貯まらいのは当然のことだ。
金持ちの特徴を3つの言葉で言い表せば「倹約、倹約、倹約」である。
「倹約」とは無駄を省く行動で、反対語は「浪費」である。
金持ちになることの意味は、金を使うことでも高いものを買うことではなく、経済的に自立すること。
自分の欲求をコントロールし、家族を立派に支え、良き夫、しつけのよい子供の父親であること。
それが彼らにとって、金持ちになる意味である。
年収10万ドル以上稼いでいても、金持ちと言える世帯は少ない。
アメリカ人の大半は、明日の金を今日使う。
ローンに追われ、稼いでは使う、使っては稼ぐというように、独楽鼠のように同じ輪の中をくるくると走りまわっている。
物をふんだんに持っていないと裕福ではないと思い込んでいる。
「守り」を重視
資産のある人は、次の3つの質問にYesと答える率が高い。
- あなたの両親は倹約家でしたか?
- あなた自身は倹約家ですか?
- あなたの妻はあなたより倹約家ですか?
結婚相手が浪費家だったら、一代で財を成すのは不可能だと思った方が良い。
年収が高いのに金持ちじゃない人は、攻めは強いが守りに弱い。
ライフスタイルを見直す必要がある。
どちらかと言えば、守りに強いほうが、攻めに強い人よりもうまく資産を築くことが多い。
億万長者は、予算を立てて出費をコントロールしたからこそ億万長者になれたし、今も裕福に暮らしている。
予算を立てなくても億万長者になった人の過半数は、まず最初に収入から貯金する分を取り分けてしまい、余った金で生活をしている。
好きなだけお金を使ってもまだお金が貯まるという羨ましい人もいる。
だが、年収が200万ドルあっても、資産が100万ドルしかなかったらどうだろう?
定義上は億万長者だが、実質的には蓄財劣等生だ。
そんな高い収入が得られる状態は長続きせず、一時的に億万長者入りしている場合がほとんどだ。
倹約家の億万長者のことを話すと、「それで幸せなんですか?」と言う人が多い。
しかし、同所得・同年齢層の中で、お金の心配をしなくて済む人たちは、そうでない人たちより幸せな生活を送っている。
教育のある高額所得者が、お金のことになるとどうしても初心になってしまう。
高学歴、高所得=経済的自立とは限らない。
経済的に自立するには、計画性と自己犠牲が必要なのだ
スコットランド系は倹約家
スコットランド系のアメリカ人で高額所得者は全米に1.7%しかいないのに、億万長者となると9.3%まで跳ね上がる。
スコットランド系は、6割の人が年収10万ドル以下で億万長者になっている。
スコットランド系には倹約家の傾向が強い。
収入が増えれば支出も増えるのが普通だが、彼らには当てはまらない。
10万ドルの年収があっても、生活費は年収8.5万ドルの世帯と同程度の支出で生活し、倹約した分貯蓄に多く回す。
2.資産形成のために時間を使う
億万長者は、資産形成のために時間、エネルギー、金を効率よく配分している。
蓄財優等生は、蓄財劣等生の2倍の時間を資産運用のために使っている。
家計予算を立てずに暮らすのは、事業計画、事業目的、会社の方針を決めずに会社を経営するようなもの。
お金持ち程、資産運用に時間をかける。
貧乏人なほど贅沢品の購入に時間をかける。
そして、高級車や高価な服などの贅沢品に使う時間と、資産運用計画に使う時間は反比例する。
良い暮らしをしたい、だから収入を増やしたいと考える人は資産家になれない。
所得水準よりも低いレベルで生活すれば、金銭感覚のしっかりした、他人に頼らずに生活できる子供が育つ。
蓄財優等生は、優等生の子供を再生産する。
3.世間体を気にしない
億万長者は、お金の心配をしないで済むことの方が、世間体を取り繕うよりもずっと大切だと考える。
蓄財劣等生、特に高額所得を得る蓄財劣等生は、使う金がほしいから働く。
次から次へと贅沢な生活を追いかけていくために働いている。
物が人を変えてしまう。
一つでもステイタス・シンボルになるような品物を手に入れると、それに併せて次から次へとものを買い足さなくなってしまう。
ステイタス・シンボルになる物と、金のかかるライフスタイルは切っても切れない関係にある。
一旦高級住宅街に住むと、稼いでは使う、使っては稼ぐというライフスタイルにハマってしまう。
アメリカでメルセデス・ベンツが7万台売れているが、全米の自動車売上台数は1,400万台なので0.5%程度しかない。
また、億万長者は350万世帯あることから考えても、億万長者の大半は高級輸入車に乗っていないことが分かる。
実際に、高級輸入車を乗り回す人の3分の2は、億万長者ではない。
4.親の経済的援助
億万長者の親は、社会人となった子供たちに経済的な援助をしていない。
親から金銭を貰った子供の財産は、逆に少なくなっていく。
親から経済的援助を受け、自分の収入で買える場所より良い地域に家を買い、子供を私立の学校に入れる。
一時的な援助かも知れないが、自分の周りに住む人との生活レベルを合わせようとすると、どうしても自分の収入に対する出費が多くなり、分不相応な生活を強いられ、お金はどんどん貯まらなくなる。
金持ちの親を持つお坊ちゃまお嬢ちゃまは、あたかも収入が沢山ある中・上流階級の一員の用に振る舞うが、そのライフスタイルは見せかけでしかない。
いつしか子供は親から与えられるお金を、自分の収入のように勘違いをしていく。
また、親の金をあてにするので、遺産相続などもあてにするようになってしまう。
一時的でも、継続的でも、親から子への経済的援助は、子供を蓄財出来ない子供にしてしまう。
教育にお金をかけるのは、子供に魚のとり方を教えるようなものだ。
億万長者の大多数が億万長者の家庭に育っていないが、確率でいえば、億万長者が億万長者の子供を生む可能性は高い。
億万長者の家庭では、メディカルスクール卒の子供のいる確率が一般家庭の5倍にもなる。
ロースクールを卒業した子供の確率は4倍である。
億万長者でない家庭から億万長者の子供が生まれる可能性は低い。
そして、その確率はどんどん低くなっている。
教育以外に子供たちにしてやれることとしては、
- 自主性を重んじる
- 一人で何かをやり遂げるように激励する
- 責任ある態度を大いに誉める
- リーダーシップを発揮した時には喜ぶ
というように、他人に頼らず一人で生きることを子供に教えるべきである。
5.経済的に自立するよう子供たちを育てる
億万長者の子供たちは、経済的に自立している。
孫に何かを与える時には、買ったモノをあげないようにしている。
また、社会的特権に結びつくものは与えない。
- 子供に両親が金持ちだと絶対に教えない
- どんなにお金があろうと子供には倹約とけじめを教えること
- 子供が安定した生活をおくるようになるまで親が金持ちと気づかせない
- 子供や孫に、何を遺産として与えるつもりか、なるべく話さない
- 現金や高価なものを駆け引きに使わない
- 巣立った子供の家庭のことには立ち入らない
- 子供と競おうと思わない
- 子供はそれぞれ違う独立した人間であることを忘れない
- 成功をもので計るのではなく、何を達成したかで計るように教育する
- 子供にお金よりも大切なものがあることを教えよう
6.ビジネスチャンスを掴む
億万長者は、ビジネスチャンスをつかむのが上手である。
ビジネスの対象を金持ち、金持ちの子供、未亡人などに絞って考えると、ビジネスの好機はたくさんある。
金持ち相手の仕事をして自分も金持ちになった人は多い。
金持ちは倹約家が多いが、創始相談、経理・税務相談、法律相談、医療・歯科治療、教育関連、住宅となるとそれほど値段に厳しくなくなる。
1,996年時点でアメリカの総世帯数は1億。
純資産100万ドル以上所有する世帯は350万(3.5%)で、その資産は全米個人資産合計の半分を占める。
金持ち相手に良いビジネスや職業
・専門分野に特化した弁護士
弁護士はたくさんいるが、有能な弁護士に対する需要は、いつの時代にも強くある。
- 相続専門の弁護士
- 税務(特に所得税と資産税)専門の弁護士
- 移民法に強い弁護士
その他、
- 医師およびヘルスケアの専門家
- 資産の鑑定・管理・売却の専門家
- 私立の教育機関と教職員
- 会計士
- 住宅関連事業
- 慈善事業
- 旅行業
7.時代にマッチした職業につく
アメリカの億万長者の大半は、自分で会社を経営している人か、独立して事務所を開いている専門職に就く人たちだ。
「独立したほうがいいでしょうか」とよく聞かれるが、大半の人は独立しても成功から程遠い人生を送っている。
億万長者が子供にすすめる進路
子供に事業を継がせる億万長者は、5人に1人でしかない。
子供が嫌がるからではなく、両親が判断して継がせない。
彼らは、事業で成功するのがいかにまれなことかを知っている。
億万長者は、以下のような専門職につき、独立して事務所を開設することを子供にすすめる。
- 医者
- 弁護士
- エンジニア
- 建築家
- 会計士
- 歯科医
億万長者は、そうでない人に比べて、メディカルスクールに子供を送る割合が5倍、ロースクールが4倍と高い。
事業に成功する確率がにくく、リスクが大きいことを億万長者は心得ている。
一方、専門職が独立する場合には、他の小規模な事業よりも利益率が高いことも知っている。
また、政府は事業を没収出来るかもしれないが、頭脳は没収できない。
そのため、医者はアメリカのどこにでも、その頭脳を持って動くことが出来る。
炭鉱業で利益を上げている会社は34%しかないが、医者は87%、獣医92%、弁護士86%が利益を上げている。
感想
倹約
億万長者というと、派手に稼いで派手に使っているイメージもありましたが、そういった類以外にも資産100万ドル(1.1億円相当)でしたら、倹約をしていくことで億万長者になっている人が多いというのは非常に有益な情報でした。
本書以外にも、資産形成に関する本でいうと「私の財産目録」「バビロンの大富豪」を読みましたが、全ての本が共通して言っているのが、「倹約」の重要性です。
本書でも、お金を貯めるには責よりも守りに強くなくてはいけないと強調されており、まさしく、「倹約」をしないで資産形成を行うということは難しいでしょう。
入ってきた給料をそのまま使うのではなく、1割~2割は先に天引きを行い貯蓄or資産運用に回していくのが理想です。
また、倹約の現代版としてはポイントやクーポン等を活用すれば無料で受けられるサービスが最近は多数あります。
乞食活動と言われたりしますが、間違いなくお金の出費を減らし、倹約に繋がる活動であると思いますので、今後も積極的に行っていきます。
親からの援助
親からの援助という項目は私にとっては一番耳が痛い話でした。
我が家の場合でいうと、子供の洋服は妻のジジババが好きで買ってくれます。
その他、妻のジジババの近所に住むことによって車を保有せず、必要な時に借りたりしています。
直接的にお金を貰っているわけではありませんが、ある意味経済的援助を受けているようなものです。
洋服や車に費用が掛からない分、浮いたお金を無駄遣いするのではなく、その分を貯蓄に回して資産形成のスピードを上げるべく気持ちを引き締めていきます。
今後も資産1億円を目指して、倹約をしていきたいところです。
この本は倹約への気持ちを駆り立ててくれる名著なので、一読をおすすめします。
私は、倹約への気持ちが薄らがないように、何度も繰り返し読んでいます。
 おとうふ
おとうふ
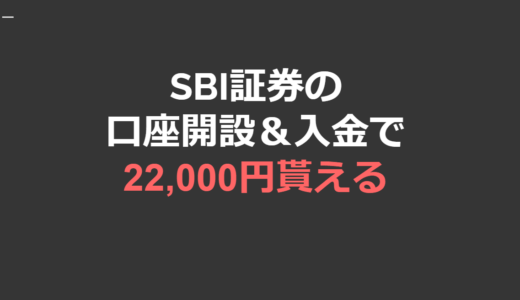 【まとめ】SBI証券で口座開設を1番お得にする方法 キャンペーン比較
【まとめ】SBI証券で口座開設を1番お得にする方法 キャンペーン比較
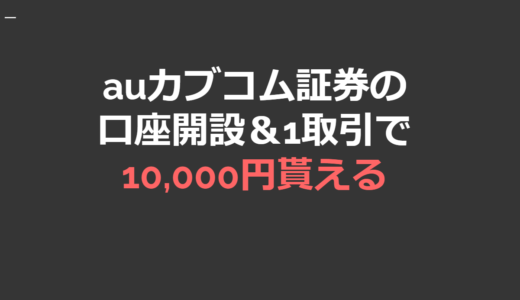 auカブコムの口座開設+1取引で11,000円相当が貰える!
auカブコムの口座開設+1取引で11,000円相当が貰える!
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1665cba7.19266542.1665cba8.03a249ae/?me_id=1213310&item_id=16530282&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3929%2F9784152093929.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3929%2F9784152093929.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

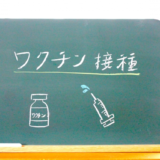
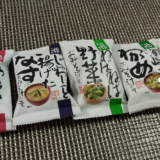
コメントを残す